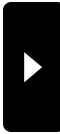2006年08月31日
タイコウチが羽化しました♪
タガメばかりに注目し過ぎていて、すっかり忘れがちなタイコウチの幼生。
昨日、あまりエサを食べていない事に心配になって、食べやすそうな大きさのエビを割り箸に挟み、目の前で揺らすと食いついてきました。

↑最初と比べると大きく成長し、捕食している姿も様になるようになりました。

↑余程お腹が減っていたのか、横で水槽の掃除をしても全く気にする様子もありません。
実はこのエサが幼虫期最後のエサとなるとは、翌朝の姿をみるまで全く気付きませんでした。

↑翌朝、飼育ケースをみてみると、タイコウチがもう1匹に!と思ったら抜け殻でした・・・^^;
更に大きく1.5倍くらいの大きさにアップ!

↑立派な成虫になりました♪背中の羽も凛々しくなりましたよ~^ o^ /
昨日、あまりエサを食べていない事に心配になって、食べやすそうな大きさのエビを割り箸に挟み、目の前で揺らすと食いついてきました。

↑最初と比べると大きく成長し、捕食している姿も様になるようになりました。

↑余程お腹が減っていたのか、横で水槽の掃除をしても全く気にする様子もありません。
実はこのエサが幼虫期最後のエサとなるとは、翌朝の姿をみるまで全く気付きませんでした。

↑翌朝、飼育ケースをみてみると、タイコウチがもう1匹に!と思ったら抜け殻でした・・・^^;
更に大きく1.5倍くらいの大きさにアップ!

↑立派な成虫になりました♪背中の羽も凛々しくなりましたよ~^ o^ /
Posted by あいる at
17:45
│Comments(2)
2006年08月30日
タイコウチの幼生の背中が黒くなってきました

↑本日も食欲旺盛な♀タガメ。真っ先に食べるのは目玉と決まっているようです。
まるで掃除機で吸い取るかのように目玉が見る見るうちに無くなります。

↑飼育ケースの中でもっとも成長著しく、最も獰猛なのがスジエビ。
網の目にも引っ掛かるのがやっとだった個体が脱皮を繰り返し、気がつけば立派な成体になっています。
1匹1匹のエビが成長した事により、水槽内の死骸処理能力は格段にアップされています。
一晩で小赤の死骸は頭蓋骨と背骨しか残っていません・・・。
♀タガメの旺盛な食欲と比例し、スジエビ達は益々食料が豊富になります。
タガメの恩恵を受けて成長するスジエビ。この飼育ケースの中で最も獰猛なのが実はこいつらなのかもしれません。
上の写真では、タガメが捕食中にタガメの腕の中にいる小赤を食べようと群がるスジエビの様子が映し出されています。

↑別の飼育ケースに入れているタイコウチの幼生。
背中に羽らしきものが出てきています。その部分だけが真っ黒。
そういえばこのタイコウチの幼生は最近めっきり捕食回数が減りました。
今まではメダカなどの小型のエサを投入していた為、比較的捕食しやすかったのでしょう。
小赤がメインになってからはうまくハンティングできていないみたいです。ちょっと心配・・・。
Posted by あいる at
19:20
│Comments(0)
2006年08月29日
金魚が真っ白・・・
久しぶりの更新になりました。
週末は電波の届かない地域に遊びに行っている事が多く、この週末はBBQしてました♪
留守にしがちな週末、家に帰って飼育ケースを見てみると金魚が減っていました。
大体1日に2匹ペース。この前仕入れてきた20匹も今となっては寂しい数になりました。

↑小赤を捕食中の♀タガメ。夏バテ知らずです!

↑食べ終わった後、金魚は鮮やかな赤色がすっかり抜けてしまい、真っ白・・・。
外部消化されてしまった状態です。強力なタガメの消化酵素。たんぱく質を分解しています。
週末は電波の届かない地域に遊びに行っている事が多く、この週末はBBQしてました♪
留守にしがちな週末、家に帰って飼育ケースを見てみると金魚が減っていました。
大体1日に2匹ペース。この前仕入れてきた20匹も今となっては寂しい数になりました。

↑小赤を捕食中の♀タガメ。夏バテ知らずです!

↑食べ終わった後、金魚は鮮やかな赤色がすっかり抜けてしまい、真っ白・・・。
外部消化されてしまった状態です。強力なタガメの消化酵素。たんぱく質を分解しています。
Posted by あいる at
13:44
│Comments(0)
2006年08月25日
コオイムシの捕食
ここ数日、例の恥ずかしい間違い発覚以来、たくさんの方々からアクセス、コメントを頂くようになりました。
先入観って怖いですね。「これがタガメの幼虫なんだ!」と思い込んでいて、それに対して何の疑念も持っていませんでしたから、今となって過去の記事を読み返すとこっ恥ずかしいです・・・汗。
ただ、これも考え方といいますか、受け止め方1つで180度変わった考えができ、この件以来多くの方とやり取りができるようになりましたし、その方々から沢山の情報を頂けるようになり、勉強になっております。
知らぬは一生の恥。一瞬の恥ずかしさで多くのものを得られた気がして、何だか変に満足しています。^^;

↑コオイムシ成虫が小赤を捕食。珍しく水面から突出した模造木の上で堪能していました。

↑コオイムシ幼生がメダカを捕食。体が小さいだけにまだ小赤はムリのようです。
何度か小赤にも果敢にアタックしていましたが、簡単に振り切られてしまっていました。
もう少し大きくなったら食べようね~。

↑大きさを比較。物凄い体格差ですね・・・。
タガメは毎日1~2匹の小赤を捕食するペースです。
捕食した事で得たエネルギーは一体何に消費しているんでしょうか・・・。
ただジーっとしているだけにしか見えないので、さほど体力消耗しているようにも見えないのですが・・・。
先入観って怖いですね。「これがタガメの幼虫なんだ!」と思い込んでいて、それに対して何の疑念も持っていませんでしたから、今となって過去の記事を読み返すとこっ恥ずかしいです・・・汗。
ただ、これも考え方といいますか、受け止め方1つで180度変わった考えができ、この件以来多くの方とやり取りができるようになりましたし、その方々から沢山の情報を頂けるようになり、勉強になっております。
知らぬは一生の恥。一瞬の恥ずかしさで多くのものを得られた気がして、何だか変に満足しています。^^;

↑コオイムシ成虫が小赤を捕食。珍しく水面から突出した模造木の上で堪能していました。

↑コオイムシ幼生がメダカを捕食。体が小さいだけにまだ小赤はムリのようです。
何度か小赤にも果敢にアタックしていましたが、簡単に振り切られてしまっていました。
もう少し大きくなったら食べようね~。

↑大きさを比較。物凄い体格差ですね・・・。
タガメは毎日1~2匹の小赤を捕食するペースです。
捕食した事で得たエネルギーは一体何に消費しているんでしょうか・・・。
ただジーっとしているだけにしか見えないので、さほど体力消耗しているようにも見えないのですが・・・。
Posted by あいる at
19:10
│Comments(2)
2006年08月24日
2006年08月23日
小赤を捕食するタガメ
衝撃の事実が発覚した翌日、♀タガメは何食わぬ顔で金魚を貪っていました。

↑久々の小赤をゲットして嬉しそうな♀タガメ。あまりの嬉しさに(?)いつもより力が入ったのか、口吻の突き刺さった付近から流血が

↑昨日羽化したコオイムシと金魚も含めてタガメの体格を比較するとその大きさが改めて分かります。

↑久々の小赤をゲットして嬉しそうな♀タガメ。あまりの嬉しさに(?)いつもより力が入ったのか、口吻の突き刺さった付近から流血が


↑昨日羽化したコオイムシと金魚も含めてタガメの体格を比較するとその大きさが改めて分かります。
Posted by あいる at
17:50
│Comments(4)
2006年08月23日
タガメの幼虫じゃない・・・
衝撃の事実です・・・。
ずっとご紹介してきたタガメの幼虫は、タガメの幼虫ではありませんでした!!
ガーン・・・
コオイムシの幼虫でした。
tagame310さんのご指摘で初めて気付く事となりましたが、見分けが付かなかった自分がお恥ずかしいです
(その他のご指摘を頂いた皆さん、ありがとうございます。)
どおりでタガメにしては丸っこいし、いつまで脱皮しても大きくならないし、前脚がやけに小さいなぁーと思っていました・・・。でもいつか大きくなるんだ!と言い聞かせていました。
(今となってはなるわけがありません。だって違う種類だもん・・・)
あまりのショックと、余計にタガメが欲しい気持ちが増したので、急遽今日もタガメの里へ行ってき、捕獲しようと試みました。片道70Kmも走って
しかし残念ながら1頭も収穫できませんでした・・・。
初めて捕りに行った日にいきなり3頭も捕れたもんで、「意外と簡単にいるもんだな」とナメていたところがありました。
うーん、やっぱり中々いるもんではないんですね。
ネットで調べると、タガメは繁殖期に特に走光性が高くなり、水銀灯での捕獲率がアップするそうです。今回捕獲できたタイミングがちょうどそれと一致した為なのでしょうか。
だとするともう今年は水銀灯の下で捕獲するのは難しそうですね。。。
とにかく、残すはメスのタガメただ1頭となってしまいました。
大事に育てなければ!
今日エサの小赤も大量に仕入れてきたので、当分はエサの確保に困る事はありません。
ずっとご紹介してきたタガメの幼虫は、タガメの幼虫ではありませんでした!!
ガーン・・・

コオイムシの幼虫でした。
tagame310さんのご指摘で初めて気付く事となりましたが、見分けが付かなかった自分がお恥ずかしいです

(その他のご指摘を頂いた皆さん、ありがとうございます。)
どおりでタガメにしては丸っこいし、いつまで脱皮しても大きくならないし、前脚がやけに小さいなぁーと思っていました・・・。でもいつか大きくなるんだ!と言い聞かせていました。
(今となってはなるわけがありません。だって違う種類だもん・・・)
あまりのショックと、余計にタガメが欲しい気持ちが増したので、急遽今日もタガメの里へ行ってき、捕獲しようと試みました。片道70Kmも走って

しかし残念ながら1頭も収穫できませんでした・・・。
初めて捕りに行った日にいきなり3頭も捕れたもんで、「意外と簡単にいるもんだな」とナメていたところがありました。
うーん、やっぱり中々いるもんではないんですね。
ネットで調べると、タガメは繁殖期に特に走光性が高くなり、水銀灯での捕獲率がアップするそうです。今回捕獲できたタイミングがちょうどそれと一致した為なのでしょうか。
だとするともう今年は水銀灯の下で捕獲するのは難しそうですね。。。
とにかく、残すはメスのタガメただ1頭となってしまいました。
大事に育てなければ!
今日エサの小赤も大量に仕入れてきたので、当分はエサの確保に困る事はありません。
Posted by あいる at
04:05
│Comments(5)
2006年08月22日
タガメがコオイムシを捕食
仕事から帰ってカバンを置くなり真っ先に向かう先はタガメの飼育ケース。
お腹ペコペコのハズなのに、自分の腹具合よりも気になるのはタガメの赤ちゃん達の様子&成長具合。
幼虫用の小さな飼育ケースを覗きこむと、昨日脱皮した幼虫ではないもう一方の幼虫も脱皮していました!

↑通常、タガメを始めとしたカメムシ科の水生昆虫(カメムシ亜目-異翅亜目 Heteroptera)は5回の幼虫期を経て成虫になります。同じ水生の昆虫で馴染み深く、当ブログでも登場したトンボの幼虫ヤゴが8~14回も脱皮する(種類によって回数が異なる)事を考えればこれでも少ないようです。
それにしても、タガメの赤ちゃんもだんだん凛々しくなってきました。立派な成虫になる日が待ち遠しいです^^ /

↑脱皮した直後でも食欲は相変わらず旺盛!5令までの幼虫期間は以下の通りだそうです。
1令期間:2~3日
2令期間:3~4日
3令期間:4~6日
4令期間:6~10日
5令期間:13日以上
ウチにいる2匹のタガメの幼生がどの段階にいるのでしょうか・・・。卵から孵化させていればちゃんとカウントできているのですが、途中で捕獲してきたものなので、正確な段階がわかりません。
もし外見の特徴で何令期の幼生であるのか見分ける方法があれば、どなたか詳しい方教えて下さいm(_ _)m
さてさて、昨日に引き続き成虫のタガメ♀ですが、こちらは再び獰猛になっていました。
エサが足りていない為でしょう、恐らく。

↑成虫用の大型のエサを初めて切らしてしまってまだ1日ですが、既にタガメのイライラはピークに近づいていました。いつものように割り箸を飼育ケースに入れて死骸をつまもうとした瞬間に割り箸へ飛び掛ってきます
この極太の腕で割り箸に抱き付かれると、ちょっとやそっとでは離れてくれません。割り箸に抱き付いた際の腕の跡が残る程のパワーです。
仕方なくメダカを与えると、少しは静かになってくれました
これだけの体格で小さなメダカでは満足するわけもないですが・・・。

↑わずか5分程度でメダカ1匹分を全て消化し終わったようです。
「ポイっと!」すてるその様子に「わたしゃーまだ空腹感が満たされてないわよ~」とでも言わんばかりの素振り。
続いてメダカをもう1匹、更にもう1匹・・・・結局この夜、一晩で6匹のメダカをお召し上がりになられました
捕食している間はおとなしいもんです。写真にあるようにスジエビが顔の周りをウロウロしても気にする様子もありません。

↑6匹のメダカを捕食してもまだ空腹感が満たされていないご様子のメスのタガメ。
今日はたまたま水槽の掃除をする為に、メスのタガメ専用ケースからコオイムシ&タイコウチ(幼生)が入っている飼育ケースに一時的に入れていました。
完全にコオイムシをロックオンした様子のタガメ。コオイムシもいつもならぬ異様な殺気に包まれている雰囲気を察したようです。
タガメは通常メスが大型の場合が多く、日本にいるメスのタガメでは最大クラスでも60mm程度。最近では60mmオーバーのクラスはごく稀なんだとか。
この写真のメスのタガメは70mm近くに達するので、間違いなく国内モノでも最大クラス!写真で比較するとその異様な大きさがよく分かると思います。

↑結局次の瞬間には捕食されてしまいました・・・。ジタバタとコオイムシが空しく暴れていましたが、この盛り上がった筋骨隆々の肉体から繰り出される「ムシ離れ」したパワーの前ではやられるがまま・・・。
この状態のタガメに割り箸で色々とちょっかいを出してみましたが、微動だにしません。

↑朝方、私がベッドに入る頃には捕食されたメダカの死骸がそこら中に散らかっている始末。
大型水槽にはスジエビが30匹近くいるので、この死骸達もあっという間にスジエビが片付けてくれます。天然の掃除機といったところでしょうか。
お腹ペコペコのハズなのに、自分の腹具合よりも気になるのはタガメの赤ちゃん達の様子&成長具合。
幼虫用の小さな飼育ケースを覗きこむと、昨日脱皮した幼虫ではないもう一方の幼虫も脱皮していました!

↑通常、タガメを始めとしたカメムシ科の水生昆虫(カメムシ亜目-異翅亜目 Heteroptera)は5回の幼虫期を経て成虫になります。同じ水生の昆虫で馴染み深く、当ブログでも登場したトンボの幼虫ヤゴが8~14回も脱皮する(種類によって回数が異なる)事を考えればこれでも少ないようです。
それにしても、タガメの赤ちゃんもだんだん凛々しくなってきました。立派な成虫になる日が待ち遠しいです^^ /

↑脱皮した直後でも食欲は相変わらず旺盛!5令までの幼虫期間は以下の通りだそうです。
1令期間:2~3日
2令期間:3~4日
3令期間:4~6日
4令期間:6~10日
5令期間:13日以上
ウチにいる2匹のタガメの幼生がどの段階にいるのでしょうか・・・。卵から孵化させていればちゃんとカウントできているのですが、途中で捕獲してきたものなので、正確な段階がわかりません。
もし外見の特徴で何令期の幼生であるのか見分ける方法があれば、どなたか詳しい方教えて下さいm(_ _)m
さてさて、昨日に引き続き成虫のタガメ♀ですが、こちらは再び獰猛になっていました。
エサが足りていない為でしょう、恐らく。

↑成虫用の大型のエサを初めて切らしてしまってまだ1日ですが、既にタガメのイライラはピークに近づいていました。いつものように割り箸を飼育ケースに入れて死骸をつまもうとした瞬間に割り箸へ飛び掛ってきます

この極太の腕で割り箸に抱き付かれると、ちょっとやそっとでは離れてくれません。割り箸に抱き付いた際の腕の跡が残る程のパワーです。
仕方なくメダカを与えると、少しは静かになってくれました

これだけの体格で小さなメダカでは満足するわけもないですが・・・。

↑わずか5分程度でメダカ1匹分を全て消化し終わったようです。
「ポイっと!」すてるその様子に「わたしゃーまだ空腹感が満たされてないわよ~」とでも言わんばかりの素振り。
続いてメダカをもう1匹、更にもう1匹・・・・結局この夜、一晩で6匹のメダカをお召し上がりになられました

捕食している間はおとなしいもんです。写真にあるようにスジエビが顔の周りをウロウロしても気にする様子もありません。

↑6匹のメダカを捕食してもまだ空腹感が満たされていないご様子のメスのタガメ。
今日はたまたま水槽の掃除をする為に、メスのタガメ専用ケースからコオイムシ&タイコウチ(幼生)が入っている飼育ケースに一時的に入れていました。
完全にコオイムシをロックオンした様子のタガメ。コオイムシもいつもならぬ異様な殺気に包まれている雰囲気を察したようです。
タガメは通常メスが大型の場合が多く、日本にいるメスのタガメでは最大クラスでも60mm程度。最近では60mmオーバーのクラスはごく稀なんだとか。
この写真のメスのタガメは70mm近くに達するので、間違いなく国内モノでも最大クラス!写真で比較するとその異様な大きさがよく分かると思います。

↑結局次の瞬間には捕食されてしまいました・・・。ジタバタとコオイムシが空しく暴れていましたが、この盛り上がった筋骨隆々の肉体から繰り出される「ムシ離れ」したパワーの前ではやられるがまま・・・。
この状態のタガメに割り箸で色々とちょっかいを出してみましたが、微動だにしません。

↑朝方、私がベッドに入る頃には捕食されたメダカの死骸がそこら中に散らかっている始末。
大型水槽にはスジエビが30匹近くいるので、この死骸達もあっという間にスジエビが片付けてくれます。天然の掃除機といったところでしょうか。
Posted by あいる at
17:29
│Comments(5)
2006年08月21日
タガメの幼虫が脱皮しました
ここ最近めっきり登場回数が減ったメスの成虫のタガメ。ちゃんと生きてますよ~o(^^)o
いつも私が見ていない時に捕食しているので、捕食シーンが撮影できていない為にブログでの出演回数が減っているだけです。

↑久しぶりに撮影できたメスの成虫タガメの捕食。捕食されたのは小型のフナ。ドジョウを捕りに行った時に網に掛かったやつです。メスタガメの飼育ケースに放り込んだエサの中で最も生存期間が長かったのですが、ついに捕食されました。
というのも、このフナ以外に今、メスタガメの飼育ケースにエサがいないのです・・・。ヤバイ!
ついにエサを切らしてしまいました・・・。
週末土曜に家から最寄のホームセンターに金魚を仕入れに行きましたが、あいにく在庫切れ。次回の入荷は8/22(火)との事です。
タガメの幼虫、タイコウチの幼虫用のエサも切らしてしまったので、仕方なくメダカを20匹購入する事に。@20円なので、400円掛かりました。
エサそのものもそうですが、天然モノのエサを捕まえに行く度に掛かっていたガソリン代や高速代など、今までにタガメ飼育の為に掛かった総費用を算出するとかなりの出費となっている事でしょう・・・。
水の手入れも手間が掛かりますし、タガメ飼育は余程の情熱と愛情が無いとやってられません。
周囲の奇異な視線もありますし・・・汗

↑2匹いるタガメの幼虫の内の1匹が脱皮しました♪(写真向かって左が抜け殻です)
こういう成長の過程を体験すると、上述の苦労や出費などを忘れて慶べます。
頑張って絶対にこの子達を立派な成虫にして長生きさせるぞぉ~!

↑脱皮したばかりのタガメの赤ちゃんは早速食欲が旺盛!
まだまだ小さな体ですが、大好物のメダカにしがみついて食べていました。

↑一度吸い付くと簡単には離れません。カメラ撮影しやすい角度に水草ごと移動させてもへっちゃらです。

↑タガメの赤ちゃんより一回り大きい体格のコオイムシもメダカを捕食しました。
「小さなタガメ」のように、コオイムシも非常に獰猛です。いっぱい食べろよ~

↑タイコウチも好物のメダカを捕食。動くものはとりあえず何でも食べる!頼もしい限りです。
タイコウチの動きは決して素早いとは言えませんが、その特徴的な大きな鎌状の前脚と、前脚にあるギザギザで巧みにターゲットを捕獲します。
死んだマネをさせるとかなりの役者ぶり!手でつまむと「オレは枯れ草だよ!」とも言わんばかりに硬直した状態で擬態します。

↑大好物のメダカの中でも最も好きなのは目玉。真っ先にそこへ口吻を持っていきます。みるみる内に目玉が無くなっていく様子が見て取れます。
いつも私が見ていない時に捕食しているので、捕食シーンが撮影できていない為にブログでの出演回数が減っているだけです。

↑久しぶりに撮影できたメスの成虫タガメの捕食。捕食されたのは小型のフナ。ドジョウを捕りに行った時に網に掛かったやつです。メスタガメの飼育ケースに放り込んだエサの中で最も生存期間が長かったのですが、ついに捕食されました。
というのも、このフナ以外に今、メスタガメの飼育ケースにエサがいないのです・・・。ヤバイ!
ついにエサを切らしてしまいました・・・。
週末土曜に家から最寄のホームセンターに金魚を仕入れに行きましたが、あいにく在庫切れ。次回の入荷は8/22(火)との事です。
タガメの幼虫、タイコウチの幼虫用のエサも切らしてしまったので、仕方なくメダカを20匹購入する事に。@20円なので、400円掛かりました。
エサそのものもそうですが、天然モノのエサを捕まえに行く度に掛かっていたガソリン代や高速代など、今までにタガメ飼育の為に掛かった総費用を算出するとかなりの出費となっている事でしょう・・・。
水の手入れも手間が掛かりますし、タガメ飼育は余程の情熱と愛情が無いとやってられません。
周囲の奇異な視線もありますし・・・汗

↑2匹いるタガメの幼虫の内の1匹が脱皮しました♪(写真向かって左が抜け殻です)
こういう成長の過程を体験すると、上述の苦労や出費などを忘れて慶べます。
頑張って絶対にこの子達を立派な成虫にして長生きさせるぞぉ~!

↑脱皮したばかりのタガメの赤ちゃんは早速食欲が旺盛!
まだまだ小さな体ですが、大好物のメダカにしがみついて食べていました。

↑一度吸い付くと簡単には離れません。カメラ撮影しやすい角度に水草ごと移動させてもへっちゃらです。

↑タガメの赤ちゃんより一回り大きい体格のコオイムシもメダカを捕食しました。
「小さなタガメ」のように、コオイムシも非常に獰猛です。いっぱい食べろよ~


↑タイコウチも好物のメダカを捕食。動くものはとりあえず何でも食べる!頼もしい限りです。
タイコウチの動きは決して素早いとは言えませんが、その特徴的な大きな鎌状の前脚と、前脚にあるギザギザで巧みにターゲットを捕獲します。
死んだマネをさせるとかなりの役者ぶり!手でつまむと「オレは枯れ草だよ!」とも言わんばかりに硬直した状態で擬態します。

↑大好物のメダカの中でも最も好きなのは目玉。真っ先にそこへ口吻を持っていきます。みるみる内に目玉が無くなっていく様子が見て取れます。
Posted by あいる at
16:29
│Comments(2)
2006年08月19日
ヤゴがタガメを捕食!
週末になると通称「タガメの里」へ向かうのが習慣となってきました。
金曜、仕事が終わってその足でクルマに乗り込み走ること片道70Km。遠い・・・。もっと近くに無いの?!とブツブツ言いながら運転。
今回初めて1人で向かったので、寂しい深夜の山道はいつもより長く長く感じました。
バックミラーで振り返るとお化けでも出てきそうな山道の1人旅。
霊感が無いみたいで、いまだに恐怖体験した事が無いので大丈夫ですが、敏感な人だとこの道中に何度か遭遇しているのでは?!と思うほど、人気の無い山道です。
さてさて、ようやく着いた「タガメの里」。いつもの水銀灯の下をくまなく探しましたが、残念ながら収穫らしき収穫はありません・・・。唯一見つけたのがタガメのオスらしき死骸。
仕方なくいつもの水田への流れ込みへ移動する事に。

↑用水路から水田へ流れ込む絶好のスポット。撮影の為に照明を付けるとウンカやヨコバイなど、小さな虫が寄って来ます。

↑湾のようになった流れ込み付近。キレイな水が絶え間なく流れ込んでいるこの場所には多くの生物が確認できます。大きなサワガニもいました。
前回のこの場所での捕獲の際に、網ですくった中身を確認しながら時間を掛けていると、Tシャツの上から背中をムシに刺されてエライ事になりました。
Tシャツの上から刺されているにも関わらず「イタイ!」と思うほどにチクリとした痛さがあり、家に帰っても痛かったので鏡で見てみると大きく3箇所が腫れ上がった状態に・・・。
蚊にしては物凄い痛みと腫れ。ブヨ?アブ?何でしょうね・・・。それから1週間近く腫れが収まりませんでした。
そんなわけで、今回はその教訓を活かして捕獲作業は迅速に!
網の中身も特に確認することなく、すくってはケースへブチ込みして帰る事に。

↑家に帰ってみると、家の飼育ケースではコオイムシがガムシを捕食している真っ最中でした。
ガムシって鳴くんですね~。知りませんでした。しかも鳴きながら水中をスイスイと泳ぎます。結構大きな音で鳴きます。
別個で小さな飼育ケースに入れている「箱入り息子?娘?」のタガメの幼虫。2個あるウチの1つを開けてみると昨日エサ用に入れていたヤゴの姿だけで、タガメの幼虫の姿がありません!
カナダモを掻き分けてみると、底に沈んだタガメの変わりきった姿が・・・。

↑何者かに食いちぎられた状態。体が斜め半分無くなっています・・・
ケースの中に居るのはスジエビとヤゴ。犯人は明らかにヤゴ!!
私の判断ミスでした。
タガメの赤ちゃんが獰猛である事を過信しすぎて、大型のヤゴを小さな飼育ケースに放り込んだのがこのタガメの赤ちゃんの命運を決めてしまいました。
「水田の王」タガメといえど、幼虫期は捕食される側。
自分の体の3~4倍の体格もある相手を捕食する「こともある」を「捕食する」と受け止めてしまっていた私の認識不足でした。
複数の生物を1つの空間に同居させた瞬間に生態系は確立されます。
今回、狭い飼育ケースに肉食である大型のヤゴと同居させたのは致命的でした。
しかもこのヤゴは数日間、超大型のメスの成虫のタガメのエサ用として成虫用ケースに入れていたので、お腹も減っていた事でしょう。捕食される側から捕食できる側へ転じたわけですから。。。

↑並べてみるとその無謀ぶりがよく分かります・・・。
ゴメンね、タガメちゃん・・・

↑トンボの幼虫ヤゴ。このムシも肉食エリート。体が全てハンティングの為に出来上がっています。
捕食における最大の特徴はこの大きな下あご。普段は折り畳んで口の下に潜ませています。

↑獲物が射程範囲内に入ると折り畳まれた大きなこの下あごを目にも止まらぬ速さで突き出します。そして獲物を自らの体へ引き寄せます。引き寄せられた獲物はヤゴの口の前に来るようになります。後は噛むだけで食べる事ができますから、何とも効率的な口と下あごの役割分担!

↑下あごの様子。昔懐かしい「先割れスプーン」のような形状をしています。
強いものが弱いものを喰う。自然界のメカニズム。
分かっちゃ~いるけども、今この飼育の対象で主役なのはあくまでも「タガメ」。
ヤゴには申し訳ないですが、またこの主役を食べるような事が起こらないよう、エサとなってもらいました。ゴメンね、ヤゴくん。。。
予想していなかったタガメの死。
今回行ってきた「タガメの里」で水田ですくった網の中にほぼ同程度の大きさのタガメの赤ちゃんが入っていました!
これで1匹死んで1匹増えた形となり、結局は同数。タガメの赤ちゃん2匹体制は変わらずです。
同じ水田で捕獲されたこの新入りタガメ。死んだタガメとは、いわば兄弟ともいえるタガメなのでしょうか。敵討ちではないですが、早速こいつにこのヤゴを与えてみました。もちろんいつものように割り箸でつまんで・・・。

↑お腹が減っていたのか、早速飛び掛りました。チクリと口吻を刺すまではヤゴが暴れ回りましたが何とか喰らい付いていました。

↑この体格差では死んだタガメもなす術もなかったでしょうね・・・。
タガメの里で収穫した飼育ケースを確認するとその他の収穫結果はガムシが1匹とスジエビが10匹程度。いずれも大きな水槽に入れ替える事にしました。

↑大きな水槽の主になりつつあるタイコウチの幼虫。脱皮してからもよく食べます。
捕ってきたばかりのスジエビを放り込んだ瞬間、たまたまタイコウチの前を通りかかったのが運のつきでした。まだ小さなスジエビは刹那にタイコウチの餌食となりました。
あまりに小さかった為、タイコウチの腹を満たせず、この後にもタイコウチは1匹のスジエビを捕食していました。
金曜、仕事が終わってその足でクルマに乗り込み走ること片道70Km。遠い・・・。もっと近くに無いの?!とブツブツ言いながら運転。
今回初めて1人で向かったので、寂しい深夜の山道はいつもより長く長く感じました。
バックミラーで振り返るとお化けでも出てきそうな山道の1人旅。
霊感が無いみたいで、いまだに恐怖体験した事が無いので大丈夫ですが、敏感な人だとこの道中に何度か遭遇しているのでは?!と思うほど、人気の無い山道です。
さてさて、ようやく着いた「タガメの里」。いつもの水銀灯の下をくまなく探しましたが、残念ながら収穫らしき収穫はありません・・・。唯一見つけたのがタガメのオスらしき死骸。
仕方なくいつもの水田への流れ込みへ移動する事に。

↑用水路から水田へ流れ込む絶好のスポット。撮影の為に照明を付けるとウンカやヨコバイなど、小さな虫が寄って来ます。

↑湾のようになった流れ込み付近。キレイな水が絶え間なく流れ込んでいるこの場所には多くの生物が確認できます。大きなサワガニもいました。
前回のこの場所での捕獲の際に、網ですくった中身を確認しながら時間を掛けていると、Tシャツの上から背中をムシに刺されてエライ事になりました。
Tシャツの上から刺されているにも関わらず「イタイ!」と思うほどにチクリとした痛さがあり、家に帰っても痛かったので鏡で見てみると大きく3箇所が腫れ上がった状態に・・・。
蚊にしては物凄い痛みと腫れ。ブヨ?アブ?何でしょうね・・・。それから1週間近く腫れが収まりませんでした。
そんなわけで、今回はその教訓を活かして捕獲作業は迅速に!
網の中身も特に確認することなく、すくってはケースへブチ込みして帰る事に。

↑家に帰ってみると、家の飼育ケースではコオイムシがガムシを捕食している真っ最中でした。
ガムシって鳴くんですね~。知りませんでした。しかも鳴きながら水中をスイスイと泳ぎます。結構大きな音で鳴きます。
別個で小さな飼育ケースに入れている「箱入り息子?娘?」のタガメの幼虫。2個あるウチの1つを開けてみると昨日エサ用に入れていたヤゴの姿だけで、タガメの幼虫の姿がありません!
カナダモを掻き分けてみると、底に沈んだタガメの変わりきった姿が・・・。

↑何者かに食いちぎられた状態。体が斜め半分無くなっています・・・

ケースの中に居るのはスジエビとヤゴ。犯人は明らかにヤゴ!!
私の判断ミスでした。
タガメの赤ちゃんが獰猛である事を過信しすぎて、大型のヤゴを小さな飼育ケースに放り込んだのがこのタガメの赤ちゃんの命運を決めてしまいました。
「水田の王」タガメといえど、幼虫期は捕食される側。
自分の体の3~4倍の体格もある相手を捕食する「こともある」を「捕食する」と受け止めてしまっていた私の認識不足でした。
複数の生物を1つの空間に同居させた瞬間に生態系は確立されます。
今回、狭い飼育ケースに肉食である大型のヤゴと同居させたのは致命的でした。
しかもこのヤゴは数日間、超大型のメスの成虫のタガメのエサ用として成虫用ケースに入れていたので、お腹も減っていた事でしょう。捕食される側から捕食できる側へ転じたわけですから。。。

↑並べてみるとその無謀ぶりがよく分かります・・・。
ゴメンね、タガメちゃん・・・


↑トンボの幼虫ヤゴ。このムシも肉食エリート。体が全てハンティングの為に出来上がっています。
捕食における最大の特徴はこの大きな下あご。普段は折り畳んで口の下に潜ませています。

↑獲物が射程範囲内に入ると折り畳まれた大きなこの下あごを目にも止まらぬ速さで突き出します。そして獲物を自らの体へ引き寄せます。引き寄せられた獲物はヤゴの口の前に来るようになります。後は噛むだけで食べる事ができますから、何とも効率的な口と下あごの役割分担!

↑下あごの様子。昔懐かしい「先割れスプーン」のような形状をしています。
強いものが弱いものを喰う。自然界のメカニズム。
分かっちゃ~いるけども、今この飼育の対象で主役なのはあくまでも「タガメ」。
ヤゴには申し訳ないですが、またこの主役を食べるような事が起こらないよう、エサとなってもらいました。ゴメンね、ヤゴくん。。。
予想していなかったタガメの死。
今回行ってきた「タガメの里」で水田ですくった網の中にほぼ同程度の大きさのタガメの赤ちゃんが入っていました!
これで1匹死んで1匹増えた形となり、結局は同数。タガメの赤ちゃん2匹体制は変わらずです。
同じ水田で捕獲されたこの新入りタガメ。死んだタガメとは、いわば兄弟ともいえるタガメなのでしょうか。敵討ちではないですが、早速こいつにこのヤゴを与えてみました。もちろんいつものように割り箸でつまんで・・・。

↑お腹が減っていたのか、早速飛び掛りました。チクリと口吻を刺すまではヤゴが暴れ回りましたが何とか喰らい付いていました。

↑この体格差では死んだタガメもなす術もなかったでしょうね・・・。
タガメの里で収穫した飼育ケースを確認するとその他の収穫結果はガムシが1匹とスジエビが10匹程度。いずれも大きな水槽に入れ替える事にしました。

↑大きな水槽の主になりつつあるタイコウチの幼虫。脱皮してからもよく食べます。
捕ってきたばかりのスジエビを放り込んだ瞬間、たまたまタイコウチの前を通りかかったのが運のつきでした。まだ小さなスジエビは刹那にタイコウチの餌食となりました。
あまりに小さかった為、タイコウチの腹を満たせず、この後にもタイコウチは1匹のスジエビを捕食していました。
Posted by あいる at
21:18
│Comments(2)


 大阪ブログポータル オオサカジン
大阪ブログポータル オオサカジン